精神分析という学問・臨床領域がある。
フロイトが創り出したといえばピンとくる方もいるだろうか。
精神分析ができる(認定を持つ)人は日本には数十名しかいないから、とてもニッチな分野である。
この領域が特殊なのは、精神分析家になるためには、自分がまず精神分析を受ける必要があるという点だ。
縁があって精神分析の亜型である精神分析的精神療法を自ら受ける機会を得て、それがどのような経験なのか記録に残すことにした。
精神科医といえども、精神分析に関しては素人だ。それがどのような学問で、どのような臨床行為なのかをきちんと書籍で体系的に勉強されたい方は、藤山直樹先生の「集中講義・精神分析」を読むと良いだろう。
精神分析、あるいは精神分析的精神療法を受けるのは、多くの場合カウンセラーの個人オフィスである。精神科病院で行なっているケースもあるが少数であろう。精神分析であれば週4〜5回、精神分析的精神療法であれば週1〜3回程度、毎週決まった曜日・時間にオフィスに通う。この濃密さ・束縛はこの領域の一つの特徴である。
オフィスにはソファやカウチが薄暗い部屋においてあり、そこに座る、もしくは横になる。カウチに横になって、その頭側に分析家が座るのが普通だ。
一般的なカウンセリングでは、調子や日々の出来事を聞かれそれに答えるような形で進んでいくと思うが、精神分析もしくは精神分析的精神療法(以下、まとめて「精神分析」と記載)においては、ひたすら「自由連想」が求められる。
「自由連想」とは、頭の中に今浮かんだことを、隠さずにありのままその場で話すことを言う。質問に答えるのではなく、まず自分が話す。頭の中に浮かんでしまったらどんなことでも分析家に話さなければいけないからとても大変である。その内容がどれほどモラルや常識に反していても、抑圧したり隠したりせず話さなければいけない。最初はこの作業に大きな抵抗や苦しみを感じるが、慣れてしまえば自然にできるようになる。しかし話したからといって何か有用な助言をしてもらえるわけでもない。さらに質問で返されたり、頷かれるだけだったり、時折無視されたりしながら、ひたすら自由連想を続ける。恥ずかしいこと、苦しいことをたくさん話すことになるから、特に最初はとても疲弊する。もう行きたくないと思うこともある。そんな作業を1回1時間程度、週に複数回、延々と繰り返すのだ。
経済的な負担も大きい。1回�のセッションは1万円前後が相場だと思うが、週1回であっても月4万円以上かかってしまう。自分の精神的な問題と向き合うためにそれだけの負担をするという覚悟は、万人が出来ることではないだろう。
②へ続く。
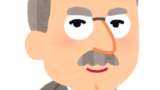
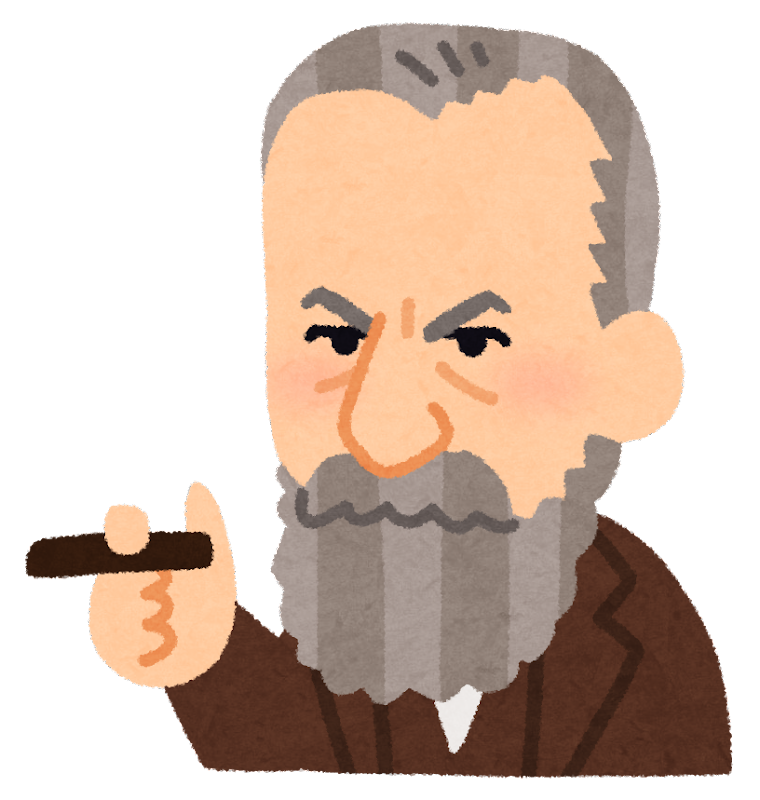

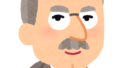
コメント