「ヴィパッサナー瞑想の教科書」(バンテ・ヘーネポラ・グナラタナ、徳間書店、2023/5)という本を読了した。
これまで読んだヴィパッサナー瞑想に関する全ての書籍の中で、一番分かりやすい入門書であると感じた。ウィリアム・ハート氏の「ゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想入門」(春秋社, 1999/11)も細かいところまで余すことなく書かれた教科書であるが、より入門者に親切な内容であると感じた。ヴィパッサナー瞑想についてきちんと勉強してみたいが、まず何から取り組んだらよいか分からない方は、まずこの書籍を読むことをお勧めしたい。下記に、要点をまとめたいと思う。
【考え方】
・どんな幸せや喜びも、感じているその瞬間は満たされた気がしているが、実はそれの終わりや、それを失うことへの不安がつきまとう。
・私たちが本当に求めているものは、何かを手に入れることではなく、何かを欲しいと思う気持ち(渇望)が消えた時に生じる心の安らぎである。
・何かを欲しいと思う気持ちにはきりがなく、たとえ次々に手に入れたとしても完璧に満たされることはなく、欲の構造を理解し、欲に支配されない方法を考えることが重要。
・不満や失望は、欲しいものを手に入れられないこと、すでに手に入れたものを失うことへの恐れ、いま持っているものに決して満足しないという心のクセから生じる。瞬間瞬間、変化している中で、何かを、何でもいいから何か安定したものにしがみつこうと探すが、そこで見つかるものといえば、しがみつけるものは何もない、変化しないものは何もない、ということである。
・すぐには不快な感情や妄想にうまく対処できないかもしれないが、いずれ出来るようになると信じる。
【瞑想の実践】
・坐る時は背筋をまっすぐに伸ばす。
・呼吸を観察するポイント(鼻孔のどこか)を見つけたら、途切れることなくその一点に集中する。
・自然な呼吸が難しい時は、呼吸をコントロールしようとする衝動を瞑想の対象にする。
・瞑想中に心の問題に対処できた力は、日常生活の中でもそのまま活かされる。
・不快な感情から逃げず、向き合い、観察する。
・退屈を感じたら、退屈を瞑想の対象にする。
・思い出や感情、妄想を抑圧しようとせず、さまざまな混乱を湧き上がらせ、過ぎ去らせる。
・第一の観察対象はいつでも呼吸であり、心が散乱したときのみ、心の散乱に意識を向け、気づき、観察し、去らせる。
・過去から身について固まっている妄想パターンに取り組んでいる場合、妄想は長いあいだ、ときには何年も、心に生まれてくる。
・妄想にあるがままに気づけば気づくほど、妄想はだんだん弱くなっていく。生じるたびに、十分な時間、十分な回数を注いで観察すれば、妄想は徐々に消えていき、いつか完全になくなる。
・欲を感じた時、その欲を観察し、欲がいかに自分を悩ませているかに気づく。
・坐って瞑想している時、気づきの対象を意図的に探さないようにする。心に現象が生まれ、その現象に気づくまで、気づきは呼吸に集中させておく。
・気づきとは、判断せずに(=言葉を使わずに)観察すること。
・真剣に気づきの実践をしようと思うならば、坐って瞑想しているときも、坐っていないときも、昼も夜も常に気づこうとする。
・「いま気づきがない」とただ気づくだけで、気づきは再確立される。
・坐る瞑想そのものは基本を練習する場であって勝負の場ではない。
・思考に対処し、絶えず湧き起こってくる感情に注意を向け続ける新しいモードを育てる。この新しい心の姿勢は、日常の他の場面にも適用することが重要。
・一日中、常に注意を払い、気づきを保つ。一秒も無駄にしないよう、できるかぎりすべての瞬間に気づく。
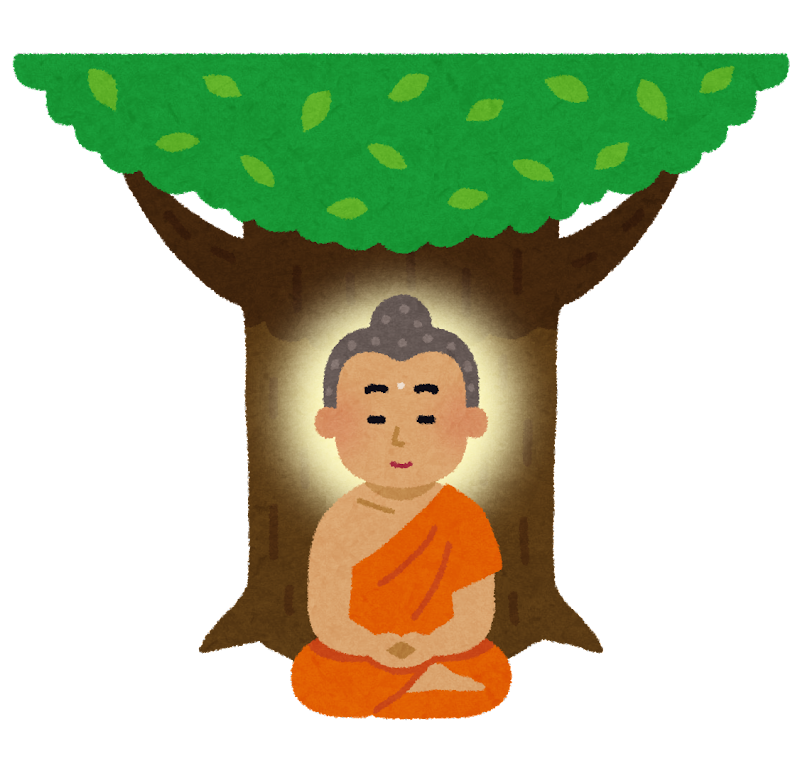


コメント