ウィリアム・ハート氏の「ゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想入門」(春秋社, 1999/11)という本に最近はまっている。学生の頃から尊敬していた「サピエンス全史」(河出書房新社, 2016/9)などで有名なユヴァル・ノア・ハラリ氏がその著書の中でヴィパッサナー瞑想を紹介しており、彼自身も1日2時間ほどヴィパッサナー瞑想をするとのことで、長らく興味を持っていた。日本ヴィパッサナー協会が京都と成田で10日間の瞑想合宿を開催していることも知っていたが、中々10日間の休みはとれず断念していた。明確なきっかけがあったわけではないが、独学の範囲でよいからきちんと勉強してみようと思い、上記の本を手に取った。
一読した感想としては、目から鱗であった。
大学生の時の授業をきっかけに瞑想に興味をもち、お寺に修行にいったりなどして、その後も瞑想やマインドフルネスに関する書籍は何冊か読んだが、この本ほど詳細に、明晰に、ごまかしなく、胡散臭さもなく、瞑想による解脱の方法を解説したものには出会ったことがなかった。(これまでに読了した瞑想・マインドフルネス関連の書籍は下記に掲載した)。
ヴィパッサナー瞑想は、ブッダが王族の地位を捨て、苦から逃れるために試行錯誤して作り上げた具体的な実践法である。
苦は「無知」・「渇望」・「嫌悪」から生じる。
解脱は、下記の順で達成される。
- 道徳(良い行動指針)を学び、実践する
- 呼吸の訓練で意識を集中させる方法を体得する
- 全身をくまなく観察し、無常・無我を経験する
現在は2の呼吸の訓練を行なっているが、1と2は理解しやすい(と思っている)。
3は、今のところは、皆目見当がつかない。
無常を経験するということは、無常を経験した者にしか分からないと本の中でも述べられており、そのあたりの記述が信憑性を高めているのだが、それにしても到底理解が及ばない。
ただ、2までを実践しているだけでも明らかに生活に良い影響がでていると感じている。
精神科臨床においてもマインドフルネス呼吸法を幾名の患者さんに紹介し、効果をあげている。
練習を続けることに価値があると思わせてくれる一冊であった。
鍛練を続け、また分かったことがあれば再度記事を書きたいと思っている。
<読了した瞑想・マインドフルネス関連書籍(順不同)>
「ゆるすということ」ジェラルド・G・ジャンポルスキー, サンマーク出版, 2006/6
「21 Lessons」ユヴァル・ノア・ハラリ, 河出書房新社, 2021/11
「始めよう。瞑想」宝彩有菜, 光文社, 2012/5
「A NEW EARTH」エックハルト・トール, サンマーク出版, 2008/10
「なぜ今、仏教なのか」ロバート・ライト, 早川書房, 2020/8
「最高の休息法」久賀谷亮, ダイヤモンド社, 2016/7
「トラウマセンシティブ・マインドフルネス」デイビッド・A・トレリーヴェン, 金剛出版, 2022/11
「身体はトラウマを記録する」ベッセル・ヴァン・デア・コーク, 紀伊國屋書店, 2016/10

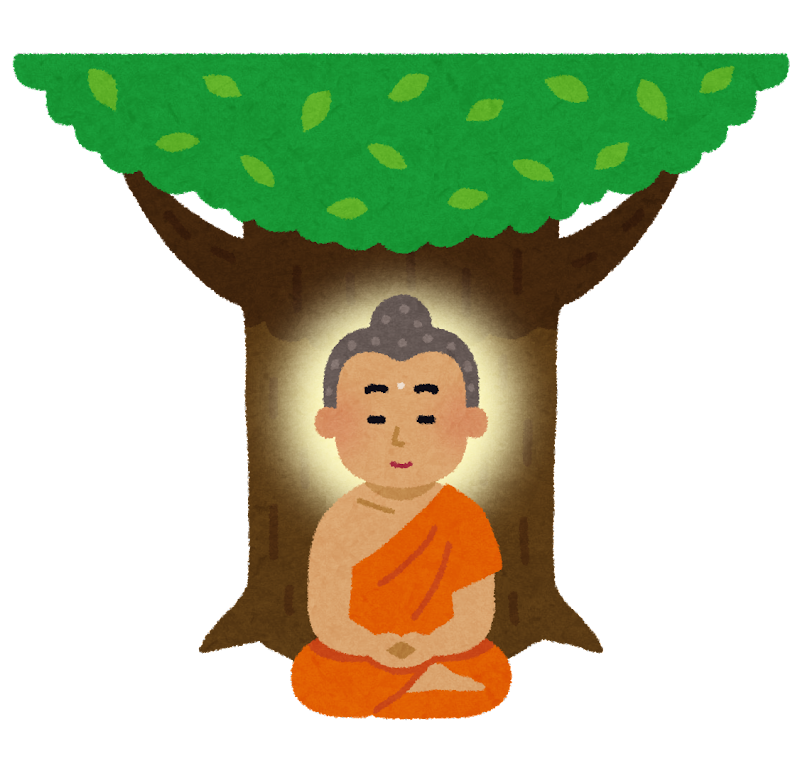
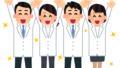

コメント
ブログを拝見させて頂きました。私は6年目なのですが、先生と同じように転科を考えていました。新内科専門医制度で専門医取得は終わったのですが、大学での雑務、研究等に追われ、バイトは稼げるかもしれませんが自分の成長になるようなものではありませんし、内科の中でも忙しい科でして、月10回程度当番をこなす生活を一生続けるのも難しいと感じてしましました。私も、もともと精神科に興味があったのですが、初期研修時の指導医の期待に応えるような形で内科を選んでしましました。いつ教授に伝えようか、そのこと考えると動悸がするほどストレスなのですが(数か月この状態で、論文もまともに読めません)、先生のブログを拝見させて頂いて勇気を頂きました。一般社会と違って、特に医局に属していると転職(転科)が一般的ではない世界ですので本当に参考になりました。感謝致します。私の場合、精神科の専門医制度に乗るのであれば2023年10月頃の応募となるのですが、それまでのおすすめの過ごし方(収入も維持しながら)はありますでしょうか。現職(大学病院スタッフ)は3月一杯まで勤務して終わりにしようと思っていて、次の勤務先は色々探してはいますがまだ決めていません。ご多忙の中申し訳ないのですが、少しでもアドバイスを頂けると大変助かります。
コメントいただきありがとうございます。参考になったとのこと、光栄です。教授に伝えることを考えて動悸がするお気持ちはよく分かります。私は幸いにも外科の医局で3月まで務め、途切れることなく4月から精神科に転科したため、実体験に基づくアドバイスはできないのですが、周りを見渡すと、①専門医プログラムにはのらないが一旦精神科病院に就職し、②翌年度からその病院で専門医プログラムにのる、というケースが散見されます。専門医プログラムにのらない就職自体はいつでも(何月という制約なく)可能ですが、翌年度から専門医プログラムにのせて貰えそうな病院を探すことが重要と考えます。毎年複数名の専攻医を募集している精神科病院(とても限られます)であれば、そういった余力もあるのではないかと思われます。その際、自分で病院を探した者もいれば、エージェントを利用した者もいます。
[…] […]